CX
公開:
2025.06.30


ヤマハ株式会社
ヤマハ株式会社
左から、
楽器事業本部 品質保証部 CSグループ
主事 松本 紘和様
主任 中村 眞由美様
音響事業本部 品質保証部 音響品質保証グループ
主事 永井 織子様
世界中から寄せられるお客さまの声を製品開発・CX向上に活かしたい 。「ファン」の声から音・音楽の未来を創るヤマハ品質保証CSの挑戦
エモーションテック 編集部
NPS活用やCX向上のためのお役立ち情報を発信しています。
世界の30以上の国・地域に拠点を持ち、楽器事業ではグローバルでNo.1*のシェアを誇るヤマハ株式会社。1887年の創業からずっとお客さま目線のものづくりを続け、心に響く音・音楽を生み出し、世界中で愛されています。 *ヤマハ調べ
アフターセールスサービスを担う品質保証部では、「ヤマハの製品をご愛用くださっているお客さまの声」をより一層ものづくりに活かすべく、2024年に「TopicScan」を導入。楽器事業本部と音響事業本部という2つの事業本部の品質保証部 CS部門で、どのようにお客さまの声を分析しているのか、また分析した結果をより広く・深く届けるための取り組みについてお話を伺いました。
本事例のサマリー
- ・お客さまの声をよりものづくりやサービスに活かすために「TopicScan」を導入
- ・グローバルな声に対して迅速かつ製品の特徴を捉えた分析が可能となり、全社でお客さまの声に向き合う仕組みを構築するうえでのスタート地点にたてた
- ・海外のお客さまサポート部門に向けた英語のレポートの共有を開始

「人」や「世代」を超えてヤマハのファンになっていただくために
ー貴社では「お客さま目線のものづくり」を大切にされていると掲げられていますが、品質保証部としてのミッション、目指す「お客さま目線」についてまずは教えてください。
松本 紘和氏(以下、松本氏):我々品質保証部は品質保証業務に加えてアフターセールス業務を担う部門であり、ヤマハの製品を実際に使ってくださっているお客さまの声が集まりやすい部署ですので、「ヤマハに好意をもっていただき使ってくださっているお客さまの目線」を、どう商品やサービスに展開していくのかというところを重要視しています。
商品企画部や開発部などでは、これからヤマハの製品を購入・使用するかもしれないお客さまの目線を想像してものづくりをしていますので、少し視点が違います。
永井 織子氏(以下、永井氏):お客さまの声が入ってくるルートはいくつかあるのですが、その中でも私たちがとりわけ重要だと認識し、分析に取り組んでいるのが「製品登録後アンケート」です。
「製品登録後アンケート」は、ヤマハの製品をご購入いただいた後にメンバー登録、お使いの製品の登録をし、その上で答えていただくアンケートになるため、お客さまにも負担がかかります。
それでも登録してお答えくださるのは、ヤマハの製品、ブランドを信頼して好意を寄せてくださっているからこそと受け止めています。そうした方々の声を製品の企画や改善に活かしていきたいと考えています。
ー松本氏は楽器事業本部、永井氏は音響事業本部と部門が分かれていらっしゃいますが、品質保証CSとして連携して取り組まれているのでしょうか。
松本氏:そうですね。お客さまからのお問い合わせ先は同じですし、「情報を継続的に収集し事業に共有していく」という取り組みも変わりません。
ヤマハの楽器をお使いでメンバーズ登録されている方が、次はヤマハの音響製品を購入された場合、すでに登録されたメンバーズ情報でログインしていただき、製品情報を加える形になります。部門として分かれてはいますが、お客さまとヤマハの接点として分断されないようにしたいと思っています。
現状は、私ども品質保証部で製品を軸としてお客さま情報を分析していますが、これからはヤマハとして「人」という軸でお客さまとの関係を積み上げていくところが目標です。例えばピアノなどの楽器は、親から子へ、子から孫へと家族で受け継がれていくことも少なからずあります。LTV(Life Time Value=顧客生涯価値)という指標がありますが、ひとつの製品が何人もの顧客との接点となることもあるのです。楽器のLTVといえるかもしれません。
人や世代を超えて、直接購入されていないお客さまにもファンになっていただき、関連商品やアフターサービスを通じて関係を継続できるようにしていきたいですね。

ーお客さま軸で体験を捉えられるようにメンバーズサービスを展開しつつ、現状は製品ごとに寄せられた声を分析するために「TopicScan」をお使いいただいているのですね。
松本氏:アンケートを中心に、ほかにもアフターサービスのところで、お客さまの困りごとを解決するためのサポート、結果や過程を通して直接いただいた声なども分析に活用しています。
「製品の特徴を捉えた分析」がスピーディにできる点が大きな魅力
ー以前からアンケートの分析をされている中で、「TopicScan」導入に至った背景をお聞かせください。
松本氏:「リソース」と「専門性」、大きく分けてこの2つに課題を感じていたことがきっかけです。
こうした分析の実務は、現在は、楽器と音響でそれぞれ数名ずつで担っています。アンケートのデータを目で見て分析するのは時間がかかりますし、一つひとつに時間がかかっていては、商品企画、開発など様々な部署からの依頼に対応しきれません。製品を販売し続けている間、断続的にお客さまからのアンケートが届きますので、分析も「一度実施したら終わり」ではありません。
継続的に声を届け続けることで、次の企画・開発にも役立ててもらえるようになります。
品質保証部では、過去からもこうしたお客さまの声の分析には取り組んでいたのですが、限られた人的リソースで継続的に取り組むための仕組みづくりには課題がある状況でした。
もう1つの「専門性」というのは、私たちの商材がバラエティ豊かなことに由来します。ホルンなどの管楽器もあればグランドピアノもあり、さらにはスピーカーやサウンドバーなどのオーディオ機器もある。使っている人も違えば、流通量も違う。楽器事業本部と音響事業本部それぞれでかなりの製品数がありますので、各製品に対して、企画開発部と同じレベルの高い専門性をもった人が分析を担当することも、今いる人たちの専門性を高めていくことも現実的ではありません。
TopicScanはLLM(大規模言語モデル)を採用していて、完全にオートで適切なトピックを抽出してくれる。これは強みかなと思います。
テキストマイニングを使いこなすには、ある程度のテクニックが必要となる印象で、やはりそこも専門性の高い人材がいないとできず、その人に依存することになりますから。
限られたリソースで、多くの製品それぞれにおいて、必要なタイミングに何度でも分析ができるような仕組みを作れないかと考えていたところに、TopicScanがはまりました。
永井氏:導入以前に、TopicScanの出力に近いことを人力で実施していました。100~500件ほどのコメントの中にどんなトピックが何件あるかという情報にまとめていました。各コメントの文脈を読み取りつつ、トピックや感情の分類をしていくため、人力だと多くの時間を費やすだけでなく、分類の判別にブレが生じやすく、毎回やり切るのは難しかったです。ただ、「大体このように言われています」という主観的なまとめ方になってしまうと、気づきを与えることには寄与できても、意思決定の根拠にはしづらく、アクションに繋げるためのハードルが高くなると感じていました。そのハードルを少しでも下げられるような有効な情報出しを継続的にできるようにしたいという想いがあり、TopicScanはそのニーズにマッチしたソリューションとして魅力を感じました。必要な情報を削ぎ落とさず、正確かつ客観的にまとめてくれます。しかも早い。TopicScanを用いることで、アクションに繋げやすい情報提供ができていると思います。

VoCを客観的に数値化できたことで見えてきた新たな価値
ー分析レポートはどのように社内に展開されていらっしゃるのでしょうか?
松本氏:社内ポータルにアップして、全社員が見られる形で共有しています。加えて、その商品の関係者に向けては個別に共有もしています。
ただ、最初からTopicScanの充実したレポートをアップしても、なかなか見てもらえません。そこで、気軽に興味を持ってもらえるように、一定のストーリーに沿った5ページほどのサマリーを作成してアップしています。
サマリーを入り口として概観を掴んでもらい、「ここってどういうこと?」と気になるポイントがあれば「詳細レポートもあるよ」とフルバージョンを共有する。今のところ、このやり方が一番効果が出ています。
そうした共有を通して分かったのですが、商品企画部や開発部のメンバーにも、アンケートやお問い合わせいただいたお客さまの「生の声」を読んでいる方が多いんです。
ただ、お客さまの声を見て「こういう意見が多い」と感じていても、定量的な情報がないので、企画や提案の根拠として提示するのに苦慮することもあったのではないかと思います。TopicScanによって、「こうした意見は○%ある」と目に見えることが大きな価値になっています。
ー分析結果を企画・開発部門でもお役立ていただいているんですね。
松本氏:お客さまが書いてくださったコメントだけですべてが読み取れるわけではないため、そのまま反映させるというわけではありません。
ただ、全体としてこういう声がどのくらいの割合あるということが数字で見えて、それが開発側で感じていたことやナレッジと一致していた際に、納得感を持って企画を推し進める力になっていると聞いています。
永井氏:「やっぱりそうだよね、やってみようか!」という形で役立ててもらえていますね。意思決定やその次のアクションに繋げるのは、もっと掘り下げる必要があるんですが、TopicScanは元の声に立ち返れるところにも可能性を感じています。
抽出されたトピックの抽象度が高くても、整理されたトピックを起点として、気になるところは元のコメントに立ち返って人の判断を加えることで、活用しやすい情報になります。

ーそれぞれの製品の分析のタイミングやサイクルは決まっているのでしょうか?
永井氏:品質保証として理想のタイミングはありますが、実際にその時々で十分な数のお客さまの声が集まっていないこともあり、時期を明確に決めるのは難しいと感じています。現状は、できるタイミングで分析をしつつ、適切なサイクルを検討中です。
松本氏:次の商品を企画する段階と、発売直後が大きなポイントです。
不満は買った直後に出るものだと思うので、そうしたタイミングで適切に声を集められるようにこれからチャレンジしていきたいと考えています。
今はスピーディに分析して、数値として届けるところを、属人化させずに仕組み化するプロセスが整いつつあるという状況です。プロセスが安定し、もっと収集や深掘りに時間がかけられるようになったら、その先の「次の示唆を導き出す」ところを目指したいですね。
海外の販売網、サービス網から上がってくるデータの分析、英語レポートの共有を開始
ーヤマハの製品は、世界各国でも愛されていますが、海外からのアンケートもそのままみなさまの元へ寄せられているのでしょうか?
中村 眞由美氏(以下、中村氏):英語、中国語に、ヨーロッパ各国の言語、ポルトガル語、スペイン語など私たちのもとに寄せられるお客さまの声の言語は多岐にわたります。日本在住で英語回答の方もいらっしゃいます。
松本氏:多言語のデータがそのまま寄せられるのですが、うまく翻訳できなさそうな表現も回答に含まれていることも多々あります。

中村氏:短い文章や、少しの情報だけではその製品に対する専門知識が十分にないと、お客さまの声を正しく理解することが難しいこともあるのですが、コメントを企画担当者に共有して、「お客さまがおっしゃっているのはこういうことだと思う」とご指摘や改善点に気づけたことがあります。
また翻訳を通すことでも、お客さまの意図と異なる表現になる可能性もあり、文章のニュアンスやお客さまの伝えたかったことを可能な限り正しく理解することを意識しておく必要があります。
お客さまの声を活用するには、分析した結果を別の観点やナレッジとつきあわせることも大切だと感じています。
松本氏:TopicScanでは多言語も一括分析ができる(※)ので、各地の販売網・サービス網から上がってくる多言語のお客さまの声の統合分析は、これから推進したいことの一つです。
今作っているレポートは、本社のメンバーを対象としているものですが、一部、TopicScanの英語レポートを海外のお客さまサポート部門に向けても配布しはじめました。
まずは、現地のサービス、セールスの感覚とお客さまの声にズレがないかを、レポートを通じて確認していくところにチャレンジしています。
※TopicScan対応言語:日本語、英語、韓国語、簡体中国語、繁体中国語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、トルコ語、ポルトガル語(ブラジル)ほか(2025年5月時点)
VoCデータの価値を高め、お客さまの声に向き合い続けられる風土醸成を目指して
ーTopicScanを使いはじめてからの変化について、どのように感じていらっしゃいますか?
永井氏:データの分類、トピック出しをするために一人でデータを見ていたときは、限られた人的リソースで、どうやったらこれらの情報を上手く正確に社内の関係者に伝えられるだろうか」と悩むことが多くありました。
企画・開発側がお客さまの声をみて「こうだろうな」と感じていた傾向を、数値として提供することで、VoCの価値をこれまで以上に感じてもらえている手応えがあります。
まだ途上ではありますが、製品登録後アンケートの結果を全社的に見ていける環境を整えていきたいと考えています。
お客さまの評価を、こうして適切に社内全体で受け止め続け、それによって必要なアクションが取れるサイクルをまわしていけるようにすることで、お客さまによりご満足いただき、よりファンになっていただくことを目指しています。
松本氏:大きな成果はこれからですが、フォーマットやサイクルを作ることは、お客さまの声と向き合うという風土を醸成するための土台となるものです。まだ入り口ではありますが、このスタート地点に立てたということがTopicScanの導入の成果だと思っています。
レポートを継続的に見てもらうことで「あそこにアクセスすれば情報がある」という認識を浸透させ、お客さまの思いと向き合う風土を全社的に育んでいきたいです。
ーTopicScanを使うようになったこの1年で、土台作りができたということですね。これからも引き続き、ファン作りの活動にお役立ていただけますと幸いです。
生成AIテキスト分析
TopicScan資料をダウンロードする
このサービス資料でわかること
- TopicScanのサービス概要
- TopicScanの独自分析技術
- 各種プランの内容



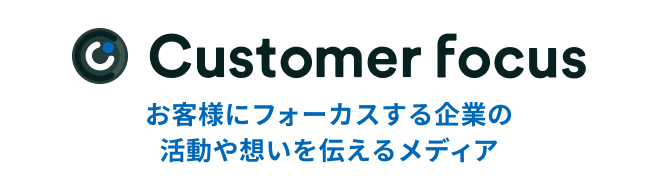



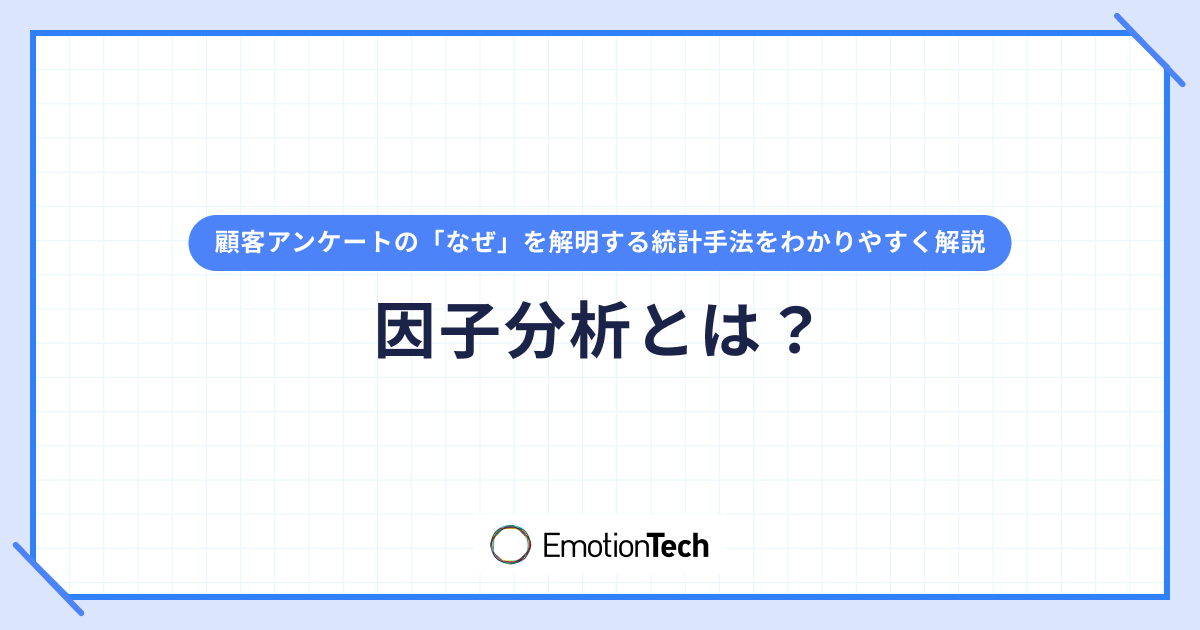




場当たり的な改善ではなく、仮説に基づいたPDCAサイクルとして推進することができています。