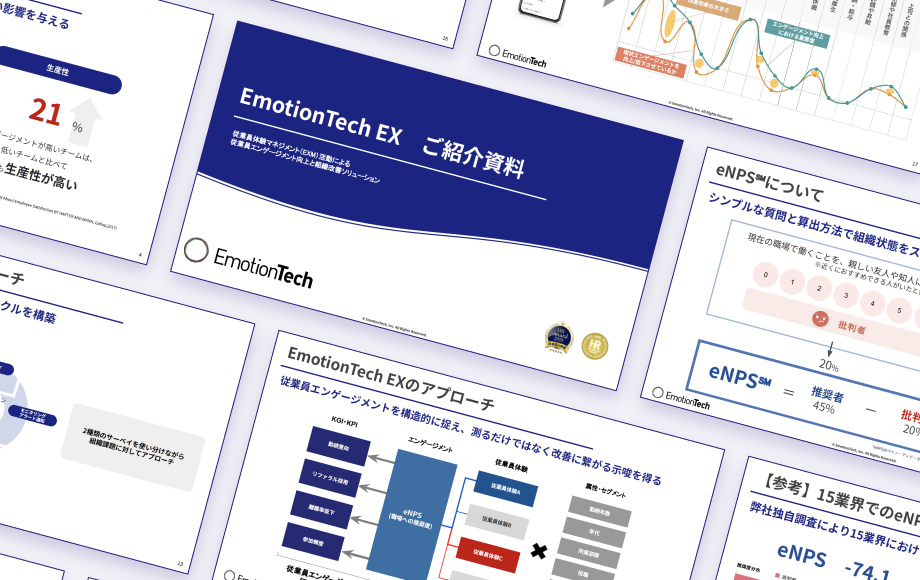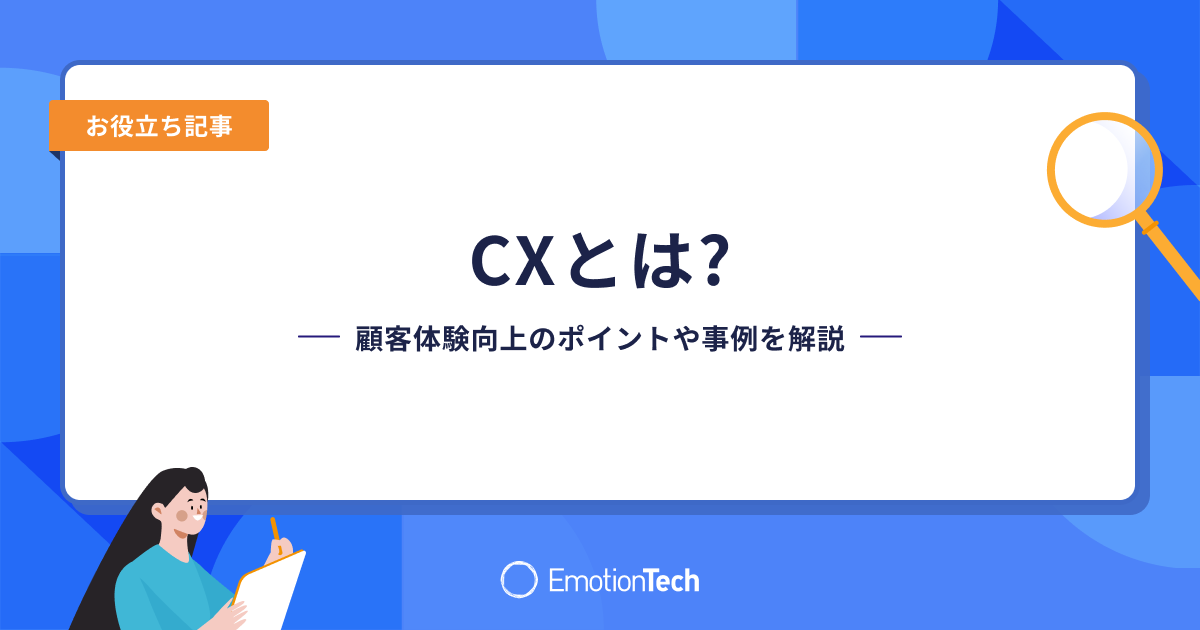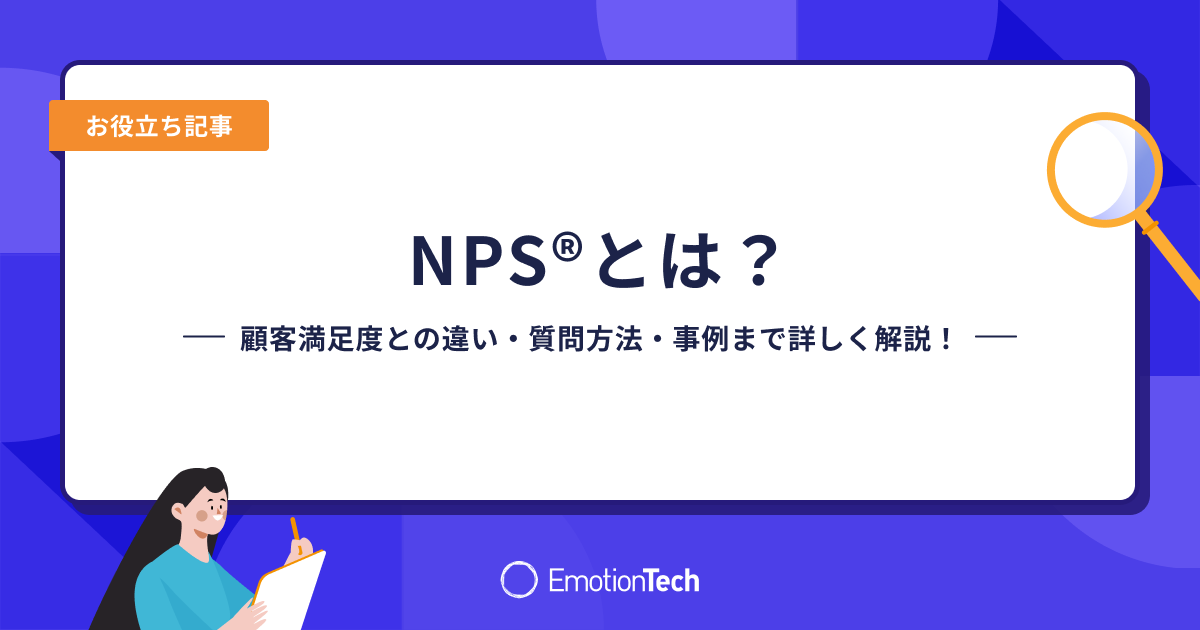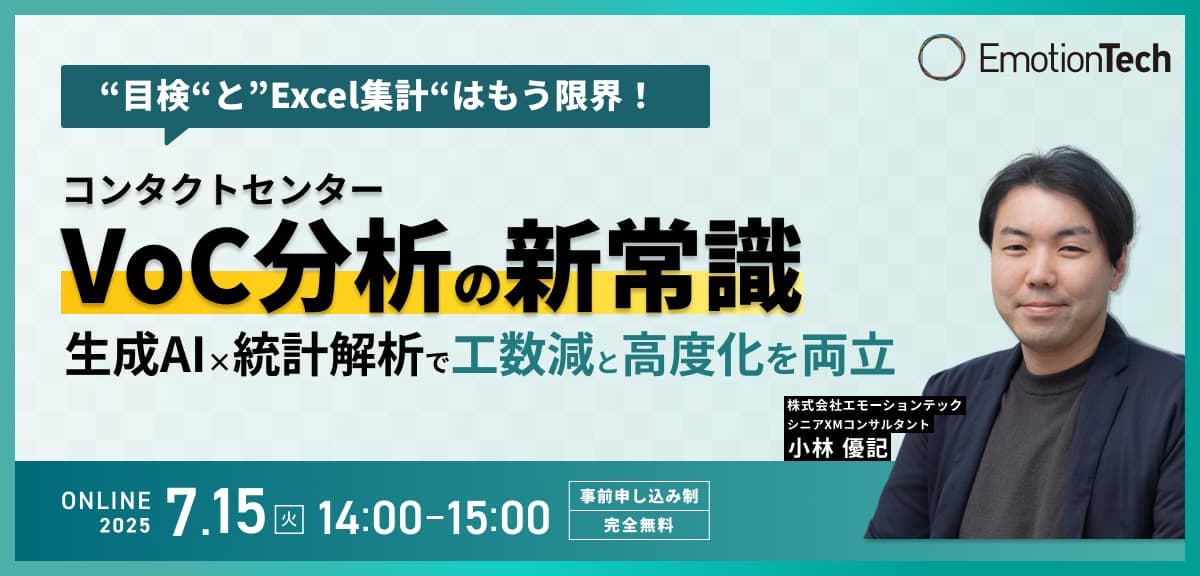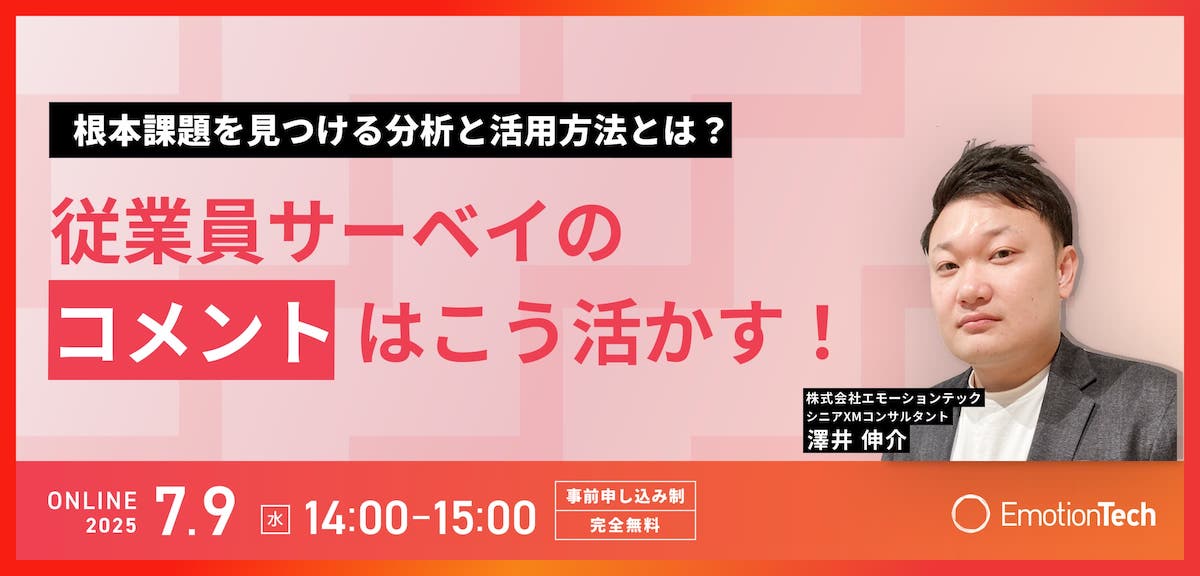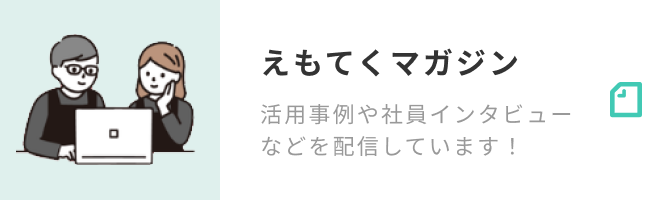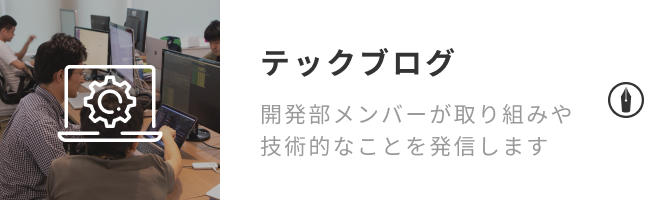従業員満足度アンケートの目的と項目作成時の注意点
更新日:2025.06.26

エモーションテック 編集部
NPS活用やCX向上のためのお役立ち情報を発信しています。
EmoitonTechのエンゲージメントサーベイ資料をダウンロードする
従業員満足度アンケートを行うことの目的
まず、従業員満足度アンケートを行う目的について見ていきましょう。
従業員の自社に対する意識を把握するため
普段、従業員が何を考え、どういった思いで業務に向かっているかを知る機会はほとんどありません。しかし、従業員満足度アンケートを行えば、一人ひとりが業務や上司、企業に対して感じる満足や不満が可視化されるのです。
それによりどのように従業員をマネジメントしていくかが掴めるため、人材育成や課題解決に役立ちます。
自社の課題を浮き上がらせるため
従業員満足度アンケートでは、業務や待遇、職場環境、上司との関係性などについて質問します。それにより、「長時間労働があった」「コミュニケーションがうまくいっていない」など、これまで見えていなかった自社の課題が分かるのです。
これを基に、業務内容の見直し、コミュニケーションの強化、福利厚生の充実といった改善が進められるでしょう。
従業員満足度を向上させる施策の効果を検証するため
従業員満足度を向上させるため、施策を行うという場合は多々あるでしょう。しかし、施策を行っただけでは適切な改善に結び付きにくいと言えます。そこで、従業員満足度アンケートによって、施策の効果が出たかどうかを検証するのです。
従業員満足度アンケートの項目を決める方法
では、従業員満足度アンケートの項目を決める方法について見ていきましょう。ここでは一般的なアンケート項目を紹介します。
総合的な項目
従業員自身が会社に対してどういった思いを持っているかを質問する項目です。愛着や信頼感を持って働いているか、現時点で離転職意向はあるか、会社自体に満足しているかどうかを質問します。
従業員満足度調査でよく用いられるのは職場の推奨度を0~10点の11段階で評価するeNPS℠という指標です。一般的な満足度を5段階で評価する指標と比べ、離職意向と強い相関を示すため、離職率を改善するという目的で調査を行う際はこの指標で社内の状況をモニタリングするのが良いでしょう。
関連記事:
eNPS℠とは?従業員エンゲージメント向上のための指標を事例付きで解説!
性別、年齢、役職、部署といった基本情報
アンケートは、従業員満足度の可視化が目的ですので、匿名ではなく必ず基本情報を記載してもらいます。
仕事に対する項目
仕事に対してどのような思いを持っているか、現状はどうか、を質問する項目です。今の業務に対するやりがいはあるか、熱意を持って臨んでいるか、面白さを感じているか、自身の成長スピードはどうか、現時点でどのぐらいの成長願望があるのかなどを質問します。
上司に対する項目
上司との人間関係について質問する項目です。コミュニケーションはしっかりと取れているか、上司に対し、リーダーシップを感じているか、上司を尊敬の念を感じて接しているかどうかを質問します。
部署、チームに対する項目
部署、チームで問題なく業務が行えているかどうかを質問する項目です。部署、チーム間でコミュニケーションに問題はないか、上司を中心にチームワークはまとまっているか、メンバー同士で互いに尊重し合える関係性を築けているかなどを質問します。
職場環境に対する項目
自身が置かれている職場の環境に満足しているかどうかを質問する項目です。業務を行ううえで過不足ない設備は整っているか、集中して業務を行える環境が用意されているか、福利厚生、資格取得のための教育研修制度が充実しているかどうかなどを質問します。
会社に対する項目
会社の方針についてどういった意識を持っているかを質問する項目です。企業風土、文化を理解し、共有できているか、経営理念やビジョン、将来性に期待を持てているかどうかを質問します。
人事評価に対する項目
会社の人事評価に対してどのように考えているかを質問する項目です。評価制度そのものや給与も含めた現在の待遇、異動、キャリア開発などについて質問します。
コンプライアンスに対する項目
会社のコンプライアンスについて、自身がどう考えているかを質問する項目です。法令やルールを遵守しているか、もしくは会社としてできているか、モラルやコンプライアンスに対する会社の取り組み姿勢に満足できているかなどについて質問します。
従業員満足度アンケートを行う際の注意点3つ
従業員満足度アンケートには、より高い効果を発揮させるための注意点があります。ここでは、そのなかでも重要な3点を紹介しましょう。
回収率を上げるため、設問数や記述を増やし過ぎない
従業員満足度アンケートの効果を発揮させるには、できるだけ細かく、深い質問が欠かせません。しかし、あまり設問数を増やしたり、回答を記述式にしてしまったりすると、回収率が落ちてしいまい、望んだ結果を得られなくなってしまいます。
従業員満足度では、従業員全体の傾向の把握はもちろん必要です。しかし、それ以上に一人ひとりの傾向を把握しなくてはならないため、少しでも回収率を高めなくてはなりません。これを実現させるためにも、設問数は10~15問程度に抑えるとよいでしょう。
また、記述式の回答欄は、特に重要な質問以外には使わないようにすると、より回収率が高まります。
目的を明確にしたうえで項目設定を行う
目的がブレていると、質問項目の設定や分析に影響を及ぼします。まず事前に目的を明確にし、それにそって自社の課題を洗い出すとよいでしょう。そこに優先順位を付けていけば、どの課題について重点的に質問するかの決定もスムーズです。仮説を立てる際のブレも減るでしょう。
1度で終わらせずに定期的に行う
従業員満足度アンケートは、実施が目的ではなく、その結果から改善につなげる点にあります。そのためにもアンケートは1回で終わらせるのではなく、定期的に行いましょう。それにより、改善策が実際に機能しているのかどうか検証できます。
検証によって改善されていなければ、なぜ改善していないのかほかの改善策がないかを考え、改善されているようであれば、また別の観点から従業員満足度アンケートを行い、同様に改善を進めましょう。従業員満足度アンケートは、こうしたサイクルを回すことで初めて、高い効果を発揮するのです。
関連記事:
従業員満足度とは?向上のメリットや調査方法について解説
従業員満足度向上のポイントは定期的な実施と効果検証
従業員満足度アンケートは、現在の従業員の状況、満足度を測るものです。よって、従業員満足度アンケートの実施だけで、満足度が向上したり自社の問題点が解決したりするわけではありません。
従業員満足度を向上させたいのであれば、明確な目的の下に従業員満足度アンケートを行い、そこで出た結果をしっかりと改善策につなげましょう。また、改善策を行う前と行った後でどういった変化が起きたかを見るためにも、定期的な実施が重要です。
従業員満足度アンケートすべての工程を把握して上手にサイクルを回していく、これは従業員満足度の向上に欠かせません。
参考:
・ 従来の顧客ロイヤルティ指標の限界、そして新たな指標となりうるNPS®の概要と活用方法|EmotionTech
・ eNPS℠とは?|EmotionTech
・ ES調査とは?そのやり方と、設計に必要な6つのステップ|Ritori
・ 従業員満足度調査に必要な9つのアンケート項目とその例文集|Torteo
よくある質問
従業員満足度アンケートはどのくらいの頻度で実施すべきですか?
施策の効果検証サイクルを回すには四半期ごと(年3〜4回)が理想です。年度単位では改善→測定の間隔が空き過ぎ、現場の温度感を拾えません。四半期であればeNPSの推移と施策効果をタイムリーに把握でき、結果を次の施策へ反映しやすくなります。
従業員満足度の指標は eNPS と ES のどちらを使うべきですか?
離職率や働きがいなどの行動指標とより強い相関を示すのは eNPS です。単一質問で推奨度を測るだけなので回答負荷が低く、分析もシンプル。ES(満足度)との併用も可能ですが、改善インパクトを定量化したい場合は eNPS を主要KPIに据えると効果検証がしやすくなります。
設問数は何問が適切?
回収率と分析精度のバランスを取るなら10〜15問が目安です。eNPS(1問)+影響要因のリッカート項目8〜10問+自由記述2〜3問で構成すると、平均回答時間は5分程度に収まり、データ粒度も確保できます。設問を増やす場合は「分析で活用しない質問を入れない」ことが鉄則です。
匿名と記名、どちらで実施するのが良いですか?
基本は匿名で実施し、安心して本音を書ける環境を作ることが重要です。ただし部署や役職などの属性は必須入力にし、傾向分析ができる粒度を担保しましょう。個人を特定したフォローが必要な場合は「特定の問い合わせ窓口へ任意で連絡できる仕組み」を別途用意すると、匿名性と個別対応の両立が図れます。
回収率を高める具体的な工夫は?
①トップメッセージで目的と活用方針を宣言し、安心感を醸成
②スマホ対応フォームとリマインダー配信で回答ハードルを下げる
③部門長・リーダーが先行回答して“回答しやすい空気”をつくる
④集計後はポジティブな結果も含めて速やかに共有し、「回答すると組織が動く」体験を提供——これらを徹底すると回収率70〜80%台が期待できます。
EmotionTechEX資料を
ダウンロードする
このサービス資料でわかること
- EmotionTech EXのサービス概要
- EmotionTechの独自分析技術
- 各種プランの内容
- 導入事例